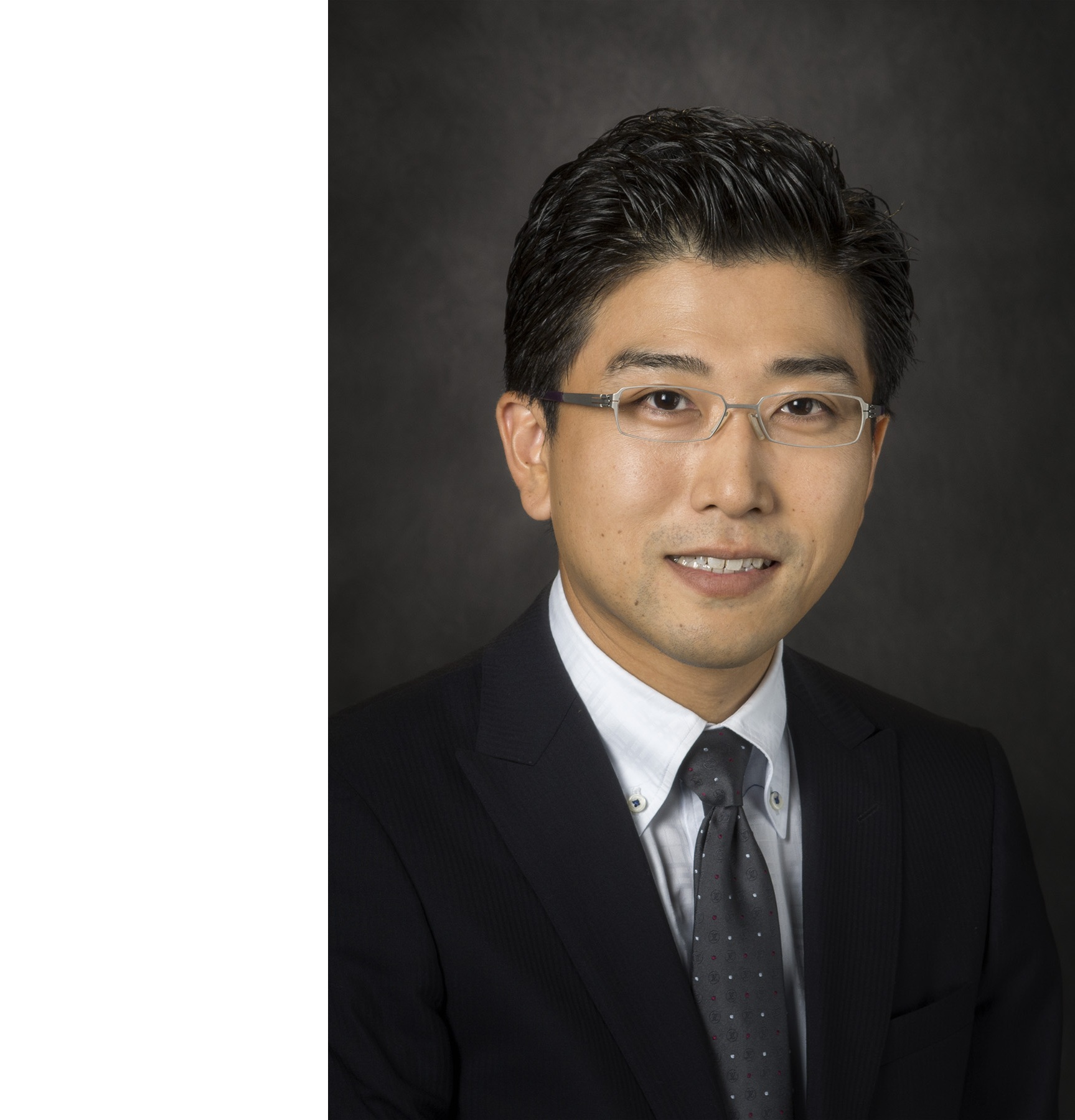新連載「Medical Innovator Interview」
テキサス大学 MDアンダーソンがんセンター
生駒成彦医師(前編)


「医療イノベーションが切り拓く未来」をテーマに、世界の最前線で活躍する医師と、リゾートトラスト株式会社メディカル本部古川本部長が、医療の進化とその可能性について語り合う対談企画が始まります。
第1回目の対談では、米国テキサス州ヒューストンにある世界有数のがん研究・治療機関「MDアンダーソンがんセンター」で腫瘍外科医として活躍する生駒成彦医師を迎え、最先端のがん治療や医療イノベーションの未来についてお話を伺います。米国の最新医療、先生のご経験を通じた日米両国の違い、臨床の現場から見た課題と展望——日本の医療で常にイノベーションを起こしてきた古川との対談だからこそ、率直で実りのある対話の時間となりました。
日米医療制度の違い
古川:日本と米国の医療制度には、それぞれ異なる特徴がありますが、日米両方を経験された先生の視点で、実際の医療現場ではどのような違いを感じられますか?また、それぞれの強みや課題について、どのような点が挙げられるでしょうか?
生駒医師:日本では国民皆保険の制度により、どの医療機関を受診しても比較的同じような治療を受けられます。しかし、アメリカでは医療格差が非常に大きく、例えばMDアンダーソンがんセンターを受診した場合と、別の病院を受診した場合では治療の結果が大きく異なることがあります。同じ治療費でも、道路を挟んで向かい側の病院に行くだけで、治療の内容や手術の質に大きな差が出ることも珍しくありません。アメリカの医療業界は非常に競争が激しく、自由競争の原理が強く働いているといえます。まさに市場経済の影響を色濃く受ける環境であり、医療の選択が治療結果に直結します。
古川:日本の医療保険や国民皆保険制度には功罪があると思います。医療費の高騰は世界共通の課題ですが、日本では国民皆保険制度のもと、「医療をビジネスにしない」というコンセプトで制度が運営されてきました。そのため、医療費が上昇し続けているとはいえ、一定の枠組みの中で抑制されている側面もあります。
生駒医師:アメリカの医療は成長を続けており、一人当たりの医療費は日本の約3倍に達しています。GDP比で見ると、アメリカは約18%、日本は約11%と、アメリカの医療費の割合は日本のほぼ倍に迫る勢いです。そのため、医療費が非常に高額となり、医療へのアクセスに大きな格差が生じています。裕福な人々は日本の平均寿命よりも長く、質の高い医療を享受できる一方で、最先端の医療を受けられない低所得層では平均寿命が短くなる傾向があります。このような医療格差は深刻な問題ですが、一方で医療のビジネス的な側面をどう捉えるかも重要な視点となります。率直に申し上げると、新しい企業や技術が生まれる背景には市場のニーズがあり、その需要に応じて医療が進化する側面も見逃せません。同じように医療も、技術革新が発展を促す、産業としての側面も重要だと感じています。
米国の研究開発を支える市場原理
たとえばアメリカで研修をしていると、メラノーマ(悪性黒色腫)とサルコーマ(肉腫)について学ぶ機会が多くあります。日本ではどちらも比較的稀な疾患ですが、アメリカではメラノーマは非常に一般的な皮膚がんである一方、サルコーマは日本と同様に稀ながんです。その結果、メラノーマに対しての研究は盛んに行われ、多額の投資が入り、ビジネスの対象となっています。そうした背景の中で新薬が次々と開発されており、その代表例が免疫チェックポイント阻害薬の「オプジーボ」です。この治療は元々メラノーマの研究から生まれましたが、現在では食道がんや胃がんなど、他の様々ながんにも適用され、がん治療の革命的な発見となりました。一方で、サルコーマの新薬は過去20年間でわずか1−2種類しか開発・承認されていません。その理由の1つは、そこにビジネスモデルがないからです。いくら優れた薬が開発されたとしても、経済的な市場規模が限られていると投資が集まりにくく、研究開発が進まないという現実があります。
米国では、医療の分野であっても、他のビジネスと同様に、市場規模や投資額によって研究の進展が左右されます。資金が投入されることで新たな技術が生まれ、それが臨床へと結びついていく。このような側面からも、医療の発展にはビジネスの視点が切り離せないことがよく分かります。
私は、医療ビジネスをポジティブに捉えています。ですから、ハイメディックの富裕層を対象にしたスクリーニングモデルから生まれた利益が、研究や開発へと回ることで、医療の発展につながっている点は、大きな意義があると思います。この流れで、今日、私がぜひお話ししたいのは「医療のバリュー」とは何か、というテーマです。医療は常に患者さん本位であるべきであり、一人ひとりの患者さんにとってのゴールとは何か、どんな価値が提供されるべきなのかを考えることが重要です。医療は単に病気を治すことだけでなく、患者さんの人生の質を向上させる役割を担うべきだと考えています。

古川:医療は本来、一人ひとりのニーズに寄り添うべきですが、現状の国民皆保険制度では、そのすべてを十分にカバーすることは難しいのが実情です。その点、ハイメディックのようなモデルは、個別のニーズや価値観に応じた医療を提供できる仕組みとして機能していると感じています。日本では公定価格が決まっているため、すべての医療サービスがその枠組みの中で提供される仕組みになっています。インバウンド向けの医療サービスを展開した場合、円安の影響もあり、海外の患者にとって日本の医療費は相対的に割安に見えることがあります。そのため、外国人向けの価格設定を導入しているケースもあるようです。しかしながら、海外の医療ツーリストがウェブサイトで日本人向けの価格と比較し、「なぜ価格が異なるのか」と不信感を抱くことも。こうした課題は、日本の医療のグローバル化と市場競争の中で、今後さらに議論が必要なテーマとなりそうです。
バリュー・ベースド・ケアという新しい視点
生駒医師:米国では医療費は病院と保険会社との交渉によって決定されます。私はコストという言葉は使いたくないのですが、米国では、病院側からすると、同じ治療成果を達成するために、どれだけ不必要な医療を削減し、コストパフォーマンスを最適化できるかが重要になります。例えば、日本では簡単な手術を受ける場合でも入院加療が一般的ですが、アメリカでは外来手術として行われるのが一般的です。日本では病床を埋めることが優先されることで必要以上に長期間入院するケースもあるようです。アメリカでは医療費の支払いシステムが異なり、1日当たりではなく、1回の入院あたりの保険支払いとなっているのが通常です。そのため、病院としては、できるだけ早く患者を退院させることでコストを最小化し、利益を確保する仕組みになっています。
このような支払い制度の違いが、医療提供の形態にも大きな影響を与えており、日本では医療のバリューにそぐわない不必要な入院が発生することもあるようです。本来であれば、質の高い手術を提供し、患者が早く回復して退院することが理想的ですが、制度の構造によって病院として取らないといけない方針が異なってしまうのが現状です。
また、米国ではどうやって「医療の質」を評価して、質の高い医療にどうやってインセンティブを与えるかが議論されてきました。そして、今注目されているのは「バリュー・ベースド・ケア」です。「量」に対する「出来高払い」から脱却し、「質」に対する報酬のあり方が求められています。がんの治療においては、単に病気が治るかどうかという結果だけでなく、患者さんがどのような社会復帰を果たせるか、精神的なダメージをどれだけ軽減できるかといった、数値では表せない要素も大きな意味を持ちます。治療の成功は単なる生存率だけではなく、患者さんの生活の質、QOLをどれだけ向上させることができるかという視点。この視点で、医療の価値を考えることが、今後の医療のあり方にとって重要だと思います。
QOL(クオリティー オブ ライフ)に着目した治療のあり方
例えば、がんを克服したとしても、治療の過程で指を失うなどの身体的な変化を経験する患者さんもいます。たとえ1本の指を失ったとしても、社会生活にほとんど影響を受けずに暮らしている人も多くいます。しかし、指を失うことで精神的な苦痛を感じる人もおり、そうした感情は数値では測れない部分があります。
古川:結局のところ、医療の価値は個々の患者の感じ方によって変わり、一人ひとりのニーズに応じたケアが求められるのではないでしょうか。
生駒医師:医師が一方的に治療方針を決定するのではなく、患者自身の価値観や希望に寄り添った選択肢を提供することが重要です。先ほどの例のように、指を切断することに対して「特に気にしない」という人もいれば、「絶対に切りたくない」と強く望む人もいます。このようなケースでは、治療の選択肢を十分に提示し、患者にとって最も価値のある医療を提供することが求められます。
この考え方とも関連するのが「シェアド・ディシジョン・メイキング(共有意思決定)」のアプローチです。従来は「パターナリスティック」モデルでは、医師がすべての治療方針を決定し、患者はそれに従う形が一般的でした。一方で、「インフォームド・コンセント」は、患者に必要な情報を提供し、その上で患者自身が治療方針を決めるという形になります。しかし、「シェアド・ディシジョン・メイキング」では、医師と患者が対話を通じて治療の選択肢を検討し、最適な方針を共同で決定します。これにより、患者の価値観や希望を尊重しながら、医療の質を向上させることができるのです。
医療の判断には、エビデンス・ベースド・メディシン(EBM)、つまり科学的根拠に基づいた選択が重要とされています。しかし、科学的な根拠だけで決定するのではなく、患者さん自身のゴールや価値観によって選択が変わるべきだと考えています。
「シェアド・ディシジョン・メイキング(共有意思決定)」の考え方に基づき、患者さんが求める治療を尊重しながら、一緒に最適な選択肢を決めていくこと。私は患者と向き合う際、「もしも私の母だったら、私はどうするか」と自分自身に問いかけます。そのような視点を持ちながら、最も良い治療選択を共に考えていくことが、医療において欠かせないプロセスだと感じています。
日本におけるハイメディックのモデルに当てはめると、単なる検査や治療の数ではなく、患者にとって最適な医療を提供し、長期的な健康維持や予防医療に貢献することが評価される仕組。こうした考え方が広がることで、医療の在り方がより患者本位の方向へと進んでいく可能性があります。
外科医が直面する現実
古川:治療の選択肢を提示できるのは、医師が周囲の状況を十分に理解し、患者のニーズを尊重する環境があるからこそ可能になります。患者のニーズに対応することが重要視される一方、近年、日本では、外科医の数が大幅に減少しているという課題があります。
生駒医師:外科医を含む医療の現場では、市場原理が大きな影響を与えています。アメリカでは、医療業界にも市場原理が働いており、外科医になりたい人が少なくなれば、外科医の給与が上昇し、それによって再び人気が高まるというサイクルが生じます。例えば、心臓外科では、仕事の負担が大きい時期に志願者が減少し、その後給与の上昇などで再び志願者が増えるといった調整機能が働いています。心臓外科医になれる人数も限定されているので、そこに競争の原理も発生するわけです。
古川:アメリカではより自由な市場原理に基づいた動きがあるようですが、日本では政府の影響力が強く、医療制度の変革が遅れるため、慢性的な問題が続いているのが現状です。減少している理由の一つとして、給与面が挙げられますが、それ以外にも労働環境や社会的評価の変化が影響していると考えられます。日本では医師が特定の診療科を選ぶ自由度が高い点が特徴ですが、リスクの高い外科医を敬遠する動きもあるようです。
生駒医師:日本では、外科医の数が減少する一方で、業務量は変わらず、一人当たりの負担が増えているのが現状です。他の診療科よりも長時間労働を強いられ、緊急対応の必要があるにもかかわらず、給与は大きく変わらない。このような環境では、「なぜ外科医を続けるのか?」という疑問が生まれるのも自然なことです。最近、学会が実施したアンケートでは、「自分の子供に外科医になることを勧めるか」という問いに対し、「勧める」と答えた外科医は 約14% にとどまりました。この結果は、多くの外科医が外科の未来に希望を持てない状況を示しています。もちろん、外科医を志す医師の多くは単に給与のために働いているわけではなく、労働時間の短縮を求めているわけでもありません。本質的な問題はそこではなく、未来への希望や、外科医としてのやりがい が感じられる環境が不足していることにあるのではないでしょうか。
「童心」まさに 私の好奇心や向上心の根源です。私は、この気持ちは決して忘れずに持ち続けたいと思いますし、さらに、外科医自身が経験した「外科医の楽しさ、誇り、やりがい」を次世代に伝えることは非常に重要です。しかし、それが難しくなるほど環境が厳しくなっているのも現実です。外科医は本当に素晴らしい職業です。研鑽を重ね、自らの腕を磨き、そして直接患者さんの命を救うことができる——これほどやりがいのある職業はそう多くありません。今後、外科医が誇りを持ち、自信を持って働ける環境を次世代に提供することが、我々の使命ではないでしょうか。

古川:日本では、子供の頃から手先を使う機会が少なくなっていると感じます。細かい作業をする経験が減ることで、将来的に手技を必要とする外科医の適性を持つ人が少なくなっているのではないかと考えています。この話に関連して、医師を志す人々の傾向が30年前と比べて変化しているのではないか、という視点もあります。特に、外科医を目指す人の数が減少し、内科など侵襲性の低い診療科が選ばれるケースが増えているのは、リスクの少なさや労働環境の変化が影響しているのかもしれません。
技術革新が切り拓く医療
生駒医師:外科医の仕事は、まさに「人の体にメスを入れる」という高い技術が求められる分野です。向き不向きはあるものの、研鑽を積み重ねることで、医師としての価値を築いていくという考え方もあります。重要なのは、自分のやりがいや目標をどこに置くかというマインドセットです。例えば、スポーツと同じように、練習を積んで技術が向上し、それを実践することで充実感を得る。このプロセスが外科医としての成長につながるのではないでしょうか。外科の分野は幅広く、手術の難易度もさまざまです。私自身、研修医の頃はヘルニアの手術が好きでしたが、経験を積むにつれてより高度な手術へと挑戦し、現在は ロボット手術による膵臓手術 など、最高難易度の手術に取り組んでいます。研修の段階ごとに目標を設定し、それを達成しながら成長していくことが、外科医としての喜びだと思います。外科医の未来を支えるためには、ロボット支援手術や新しい技術の活用が欠かせません。新たな技術を取り入れることで、外科医療の可能性を広げ、外科医を志す若者に希望を与えることができるはずです。次世代の外科医が憧れを持ち続けられるような環境を整え、外科医という職業が輝き続ける未来を築いていくことこそ、私の使命の一つだと思っています。 (後編につづく)