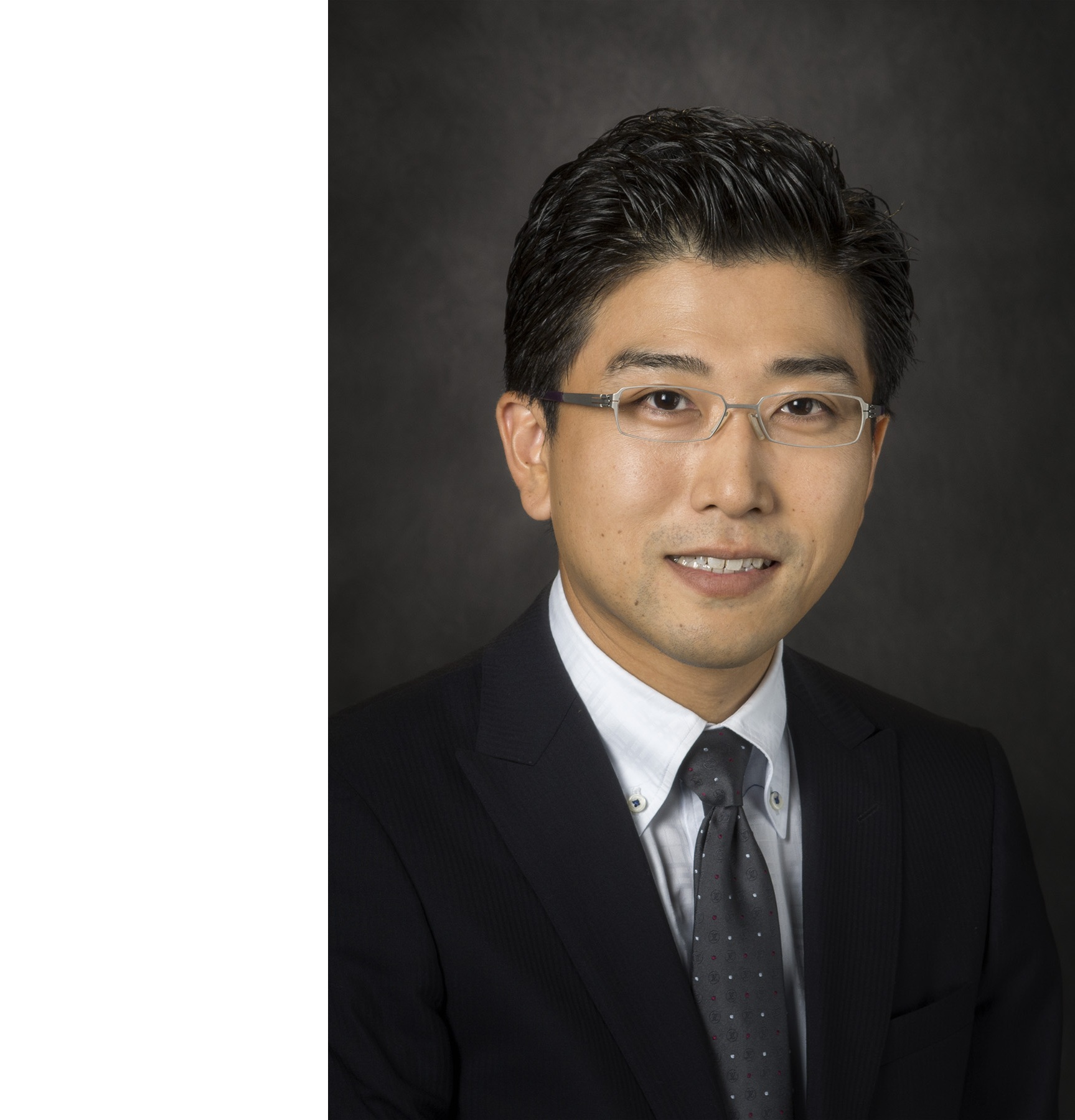新連載「Medical Innovator Interview」
テキサス大学 MDアンダーソンがんセンター
生駒成彦医師(後編)

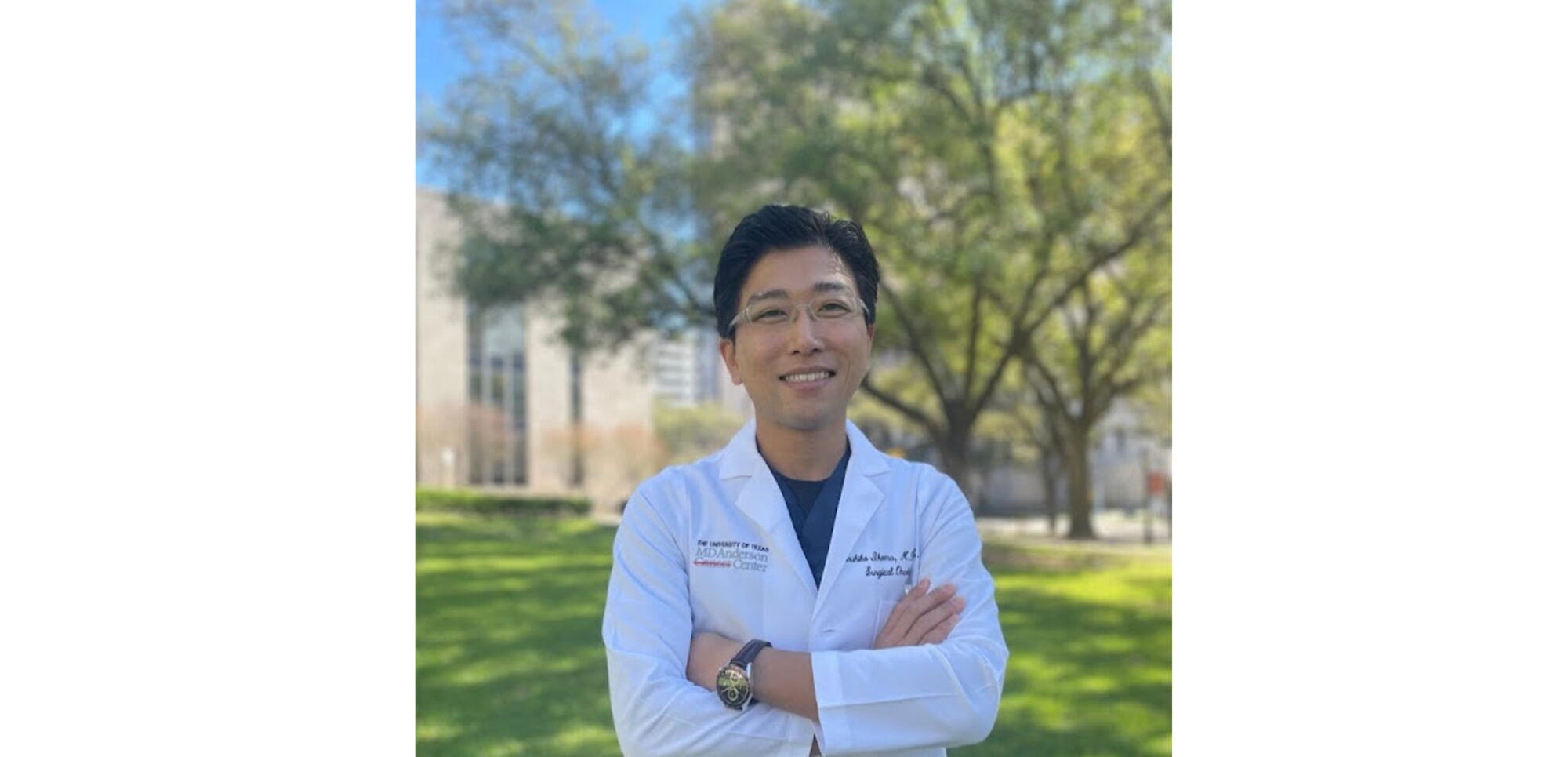
「医療イノベーションが切り拓く未来」をテーマに、世界の最前線で活躍する医師と、リゾートトラスト株式会社メディカル本部古川本部長が、医療の進化とその可能性について語り合う対談企画が始まりました。
第1回目の対談では、米国テキサス州ヒューストンにある世界有数のがん研究・治療機関「MDアンダーソンがんセンター」で腫瘍外科医として活躍する生駒成彦医師を迎え、最先端のがん治療や医療イノベーションの未来についてお話を伺います。前編では、米国の最新医療、先生のご経験を通じた日米両国の違い、臨床の現場から見た医療の課題と展望についてお話を伺いました。後編では、先生の専門であるロボット支援手術について、そして医療の未来について詳しくお話をうかがいます。
医療技術の飛躍:ロボット支援手術の可能性
古川:ロボット支援手術は、医療技術の飛躍的な進歩として注目されています。専門である先生に詳しくお話をうかがいたいと思います。
生駒医師:ロボット支援出手術は、ロボットが自動的に手術するわけではなく、人間の医師がロボットを操作して行います。腹腔鏡手術はポートを通して患者の腹腔内に挿入した鉗子を医師が直接操作しますが、ロボット手術ではロボットアームの先端に遠隔操作できる鉗子が取り付けられていて、医師は特殊なコントローラーでロボットを操作することによって手術を行います。普通の外科手術とロボット外科手術の違いについて、多くの方が気になるのは安全性や正確性といった点ではないかと思いますが、それぞれにメリットがあります。

一般的にロボット手術では人間のような手の震えがなく、細かく正確な作業ができる利点があります。さらに、「傷が小さい」と言われることが多いですが、私自身はそれほど重要な要素ではないと考えています。膵臓がんや胃がんの手術は、人生に一度きりの大手術となることが多く、患者さんが求めるものは、単に傷が小さいことではないと思います。重要なのは、ロボット技術を駆使し、できるだけ正確に、そして安全に手術を行うこと。そして、患者さんの生活の質(QOL)を損なうことなく、できるだけ早い社会復帰を支援することだと考えています。
現在でも先端技術が導入され、ロボット手術の精度は向上し続けています。さらに今後は、AI技術の進化によって、手術の安全性や効率が飛躍的に向上し、より患者さんの負担を軽減できる医療が実現していくでしょう。
古川:ロボット手術には多くのメリットがありますが、一方で、苦手な部分や限界がありますか。ロボット手術の課題にはどのような点があるのでしょうか?
生駒医師:ロボット手術にも苦手な部分があります。例えば、ダイナミックな動きが不得意という点が挙げられます。一般手術であれば、手を使って臓器を動かして視野を確保できますが、ロボット手術では精密な動きに優れている反面、大きな動作を一度に行うことが難しいため、工夫して補う必要があります。また、出血時の対応も課題の一つです。人間が行う手術であれば、医師が手で直接圧迫して止血できますが、ロボット手術では先端が細かいため、すぐに出血を抑えられないケースがあります。そのため、止血の技術や出血させない戦略がより重要になります。
日本的価値観と技術革新のジレンマ
古川:日本人の感覚として、放射線科の画像診断や手術においても、「人間が直接行った方が良い」という価値観が根強く残っているように感じます。これは、特に医師や患者の間で強く意識される傾向があるようです。AIを活用した診断や予防的手術が進化する中でも、「やはり人間が行う方が価値が高い」という考え方が一定の支持を得ています。心臓外科の分野でもそうした議論があり、放射線科におけるAIの導入も慎重に進められているのが現状です。技術の発展と伝統的な医療の価値観がどのように融合していくか、今後の課題として注目されるポイントです。
生駒医師:「人間が判断する方が良い」という価値観は、日本では根強く残っていそうですね。確かに、医療分野では、AIやロボット手術に対して慎重な姿勢が見られます。しかし、今はまさにデータサイエンスの時代であり、医療技術の進化によって、こうした考え方も変わりつつあると感じています。AIの進化は加速しており、自動手術の時代も近づいています。例えば、自動運転が予測困難な環境での対応を求められるのに対し、手術はコントロールされた環境で行われるため、実は技術的に自動化が進みやすい分野ではないかとも考えられます。責任の問題をクリアすれば、AIの活用による医療の効率化や安全性向上が期待されます。
2045年にはAIが人類全体の知能を超えると予測されており、手術の分野でも「AIを使わない方が危険」と考えられる時代が来るかもしれません。ボードゲームの進化と同様に、AIは自ら最適な判断を生み出し続け、医療分野でも人間の介入が減る未来は、もはや時間の問題かもしれません。
古川:責任の所在を明確にすることは重要ですが、それを支えるのはデータサイエンスの力です。過去の数値を分析し、「10%だった割合が5%に減少した」など、科学的な視点で物事を判断することが求められます。冷静なデータ分析によって実際のリスクを正しく評価することが必要です。「全体としてリスクが減少している」と明確に示し、科学的根拠をもとに国民を導く指導力が重要です。日本ではポピュリズムの影響が強く、感情的な議論に流されがちですが、本当に求められるのは 強いリーダーシップ ではないでしょうか。そうしたリーダーの存在が、冷静かつ合理的な社会の構築につながるのではないかと考えます。
ハイメディックの意義と未来
古川:ここでもう一つ、別の質問をさせてください。生駒先生が考えるハイメディックの存在意義や、今後の展望についてお聞かせください。ハイメディックが果たすべき役割や期待されることについて、先生の視点からお話しいただければと思います。
生駒医師:ハイメディックの検診だからこそ得られる網羅的で継続的なデータには、今後の検診医療において大きな価値があると感じています。例えば、ハイメディックがサポートされているサリバテックの研究で、ある時点で唾液中のメタボロームに変化が見られ、その後、精密検査でがんが発見されたというようなエピソードは、こうした長期的なデータ蓄積の重要性を示しています。このようなデータは、単なるクロスセクショナル(単一時点)なスクリーニングでは得られないものであり、長期的な視点での追跡研究によって初めて見えてくるものです。
BNCT(ホウ素中性子捕捉療法)などの世界をリードする先端がん治療の研究開発も含め、ハイメディックならではのデータを積極的にアウトプットし、それを医療のさらなる革新につなげることが重要だと思います。画像診断データや血液バイオマーカーなどを組み合わせ、長期的な測定を行うことができる点は、他にはないユニークな強みです。
また、日本の国民皆保険制度では対応しきれない高度な医療にもチャレンジできることは、ハイメディックの強みの一つです。特に、アカデミックセンターとのコラボレーションにより、大学病院では単独で実現しにくい研究や医療技術の発展を推進できる点は、大きな意義を持つと思います。